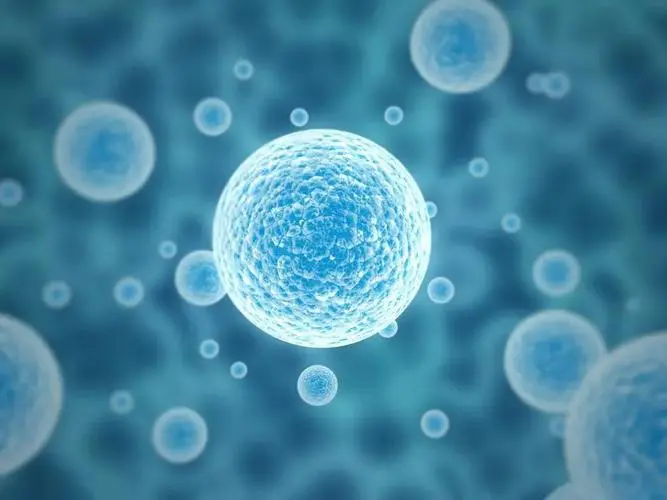酸素療法は現代医学で最も一般的に使用されている方法の1つですが、酸素療法の適応については依然として誤解があり、酸素の不適切な使用は深刻な毒性反応を引き起こす可能性があります。
組織低酸素症の臨床評価
組織低酸素症の臨床症状は多様かつ非特異的であり、最も顕著な症状としては呼吸困難、息切れ、頻脈、呼吸窮迫、急激な精神状態の変化、不整脈などが挙げられます。組織(内臓)低酸素症の有無を判断するには、血清乳酸値(虚血および心拍出量低下時に上昇)とSvO2値(心拍出量低下、貧血、動脈性低酸素症、高代謝時に低下)が臨床評価に役立ちます。しかし、乳酸値は低酸素状態以外でも上昇する可能性があるため、乳酸値の上昇のみに基づいて診断することはできません。また、悪性腫瘍の急速な増殖、早期敗血症、代謝障害、カテコールアミン投与など、解糖が亢進する状態においても乳酸値は上昇することがあります。クレアチニン、トロポニン、肝酵素の上昇など、特定の臓器の機能不全を示すその他の臨床検査値も重要です。
動脈血酸素化状態の臨床評価
チアノーゼ。チアノーゼは通常、低酸素症の後期に現れる症状であり、貧血や血流灌流不良では現れない場合があり、また肌の色が濃い人はチアノーゼを検出するのが難しいため、低酸素血症や低酸素症の診断においては信頼性が低い場合が多いです。
パルスオキシメトリーモニタリング。非侵襲性パルスオキシメトリーモニタリングは、あらゆる疾患のモニタリングに広く利用されており、その推定SaO2はSpO2と呼ばれます。パルスオキシメトリーモニタリングの原理はビルの法則であり、溶液中の未知の物質の濃度は光の吸収によって決定できるというものです。光が組織を通過すると、そのほとんどは組織の成分と血液に吸収されます。しかし、心臓の拍動ごとに動脈血は脈動するため、パルスオキシメトリーモニターは660ナノメートル(赤色)と940ナノメートル(赤外線)の2つの波長における光吸収の変化を検出できます。還元ヘモグロビンと酸化ヘモグロビンの吸収率は、これらの2つの波長で異なります。脈動のない組織の吸収を差し引くことで、総ヘモグロビンに対する酸化ヘモグロビンの濃度を計算できます。
パルスオキシメトリーのモニタリングにはいくつかの制限があります。これらの波長を吸収する血液中の物質は、測定精度に影響を与える可能性があります。これには、一酸化炭素ヘモグロビンやメトヘモグロビン血症などの後天性異常ヘモグロビン症、メチレンブルー、特定の遺伝性ヘモグロビン変異体が含まれます。660ナノメートルの波長における一酸化炭素ヘモグロビンの吸収は、酸素化ヘモグロビンの吸収と似ています。940ナノメートルの波長では吸収が非常に小さいです。したがって、一酸化炭素飽和ヘモグロビンと酸素飽和ヘモグロビンの相対濃度に関係なく、SpO2は一定(90%~95%)を維持します。メトヘモグロビン血症では、ヘム鉄が第一鉄状態に酸化されると、メトヘモグロビンが2つの波長の吸収係数を均等にします。その結果、メトヘモグロビンの比較的広い濃度範囲内で、SpO2は83%~87%の範囲内でしか変化しません。この場合、動脈血酸素測定では、ヘモグロビンの 4 つの形態を区別するために 4 つの光の波長が必要です。
パルスオキシメトリーモニタリングは、十分な脈動血流に依存します。そのため、ショックによる低灌流状態や、非脈動性心室補助装置(心拍出量が心拍出量のごく一部に過ぎない状態)の使用時には、パルスオキシメトリーモニタリングは使用できません。重度の三尖弁逆流症では、静脈血中の脱酸素ヘモグロビン濃度が高く、静脈血の脈動により血中酸素飽和度が低くなる可能性があります。重度の動脈性低酸素症(SaO2<75%)では、この技術がこの範囲で検証されたことがないため、精度が低下する可能性があります。最後に、肌の色が濃い人が使用する特定のデバイスによっては、パルスオキシメトリーモニタリングが動脈血ヘモグロビン飽和度を最大5~10パーセントポイント過大評価する可能性があることに気付く人が増えています。
PaO2/FIO2比(一般的にP/F比と呼ばれ、400~500 mmHgの範囲)は、肺における異常な酸素交換の程度を反映し、機械的人工呼吸器によってFIO2を正確に設定できるため、この状況において最も有用です。AP/F比が300 mmHg未満の場合、臨床的に有意なガス交換異常を示し、P/F比が200 mmHg未満の場合、重度の低酸素血症を示します。P/F比に影響を与える要因には、換気設定、呼気終末陽圧(PEO)、FIO2などがあります。FIO2の変化がP/F比に与える影響は、肺損傷の性質、シャント率、およびFIO2の変化範囲によって異なります。PaO2が測定できない場合、SpO2/FIO2が適切な代替指標となります。
肺胞動脈血酸素分圧(Aa PO2)差。Aa PO2差は、計算された肺胞酸素分圧と測定された動脈血酸素分圧の差であり、ガス交換の効率を測定するために使用されます。
海面で周囲の空気を呼吸する場合の「正常な」Aa PO2 差は、年齢によって異なり、10~25 mm Hg(2.5+0.21 x 年齢[歳])の範囲です。2 つ目の影響要因は FIO2 または PAO2 です。これら 2 つの要因のいずれかが増加すると、Aa PO2 の差は拡大します。これは、肺胞毛細血管でのガス交換が、ヘモグロビン酸素解離曲線のより平坦な部分(傾斜)で発生するためです。同じ程度の静脈混合では、混合された静脈血と動脈血の PO2 の差は拡大します。逆に、換気が不十分であったり標高が高いために肺胞 PO2 が低い場合、Aa 差は正常よりも低くなり、肺機能障害の過小評価や不正確な診断につながる可能性があります。
酸素化指数。酸素化指数(OI)は、人工呼吸器を装着している患者において、酸素化を維持するために必要な換気補助の強度を評価するために用いられます。酸素化指数には、平均気道内圧(MAP、cm H2O)、FIO2、PaO2(mm Hg)またはSpO2が含まれ、40を超える場合は体外式膜型人工肺(EMT)の基準として用いられます。正常値は4 cm H2O/mm Hg未満です。cm H2O/mm Hgは均一な値(1.36)であるため、この比率を報告する際には通常、単位は含めません。
急性酸素療法の適応
患者が呼吸困難を呈した場合、通常は低酸素血症と診断される前に酸素補給が必要です。動脈血酸素分圧(PaO2)が60mmHgを下回る場合、酸素摂取量の最も明確な指標は動脈性低酸素血症であり、これは通常、動脈血酸素飽和度(SaO2)または末梢酸素飽和度(SpO2)が89%~90%に相当します。PaO2が60mmHgを下回ると、血中酸素飽和度が急激に低下し、動脈血酸素含有量の大幅な減少につながり、組織低酸素症を引き起こす可能性があります。
動脈性低酸素症に加えて、まれに酸素補給が必要になる場合があります。重度の貧血、外傷、および外科的重篤患者では、動脈血酸素濃度を上昇させることで組織の低酸素症を軽減できます。一酸化炭素(CO)中毒患者の場合、酸素補給により血液中の溶存酸素量が増加し、ヘモグロビンに結合したCOが補充され、酸素化ヘモグロビンの割合が増加します。純酸素を吸入した場合、一酸化炭素ヘモグロビンの半減期は70~80分ですが、外気を吸入した場合の半減期は320分です。高圧酸素条件下では、一酸化炭素ヘモグロビンの半減期は純酸素吸入後10分未満に短縮されます。高圧酸素は、一般的に一酸化炭素ヘモグロビン濃度が高い(> 25%)、心虚血、または感覚異常がある場合に使用されます。
裏付けとなるデータが不足しているか不正確であるにもかかわらず、酸素補給が有益となる可能性のある疾患は他にもあります。酸素療法は、群発性頭痛、鎌状赤血球症性疼痛発作、低酸素血症を伴わない呼吸窮迫の緩和、気胸、縦隔気腫(胸部空気の吸収促進)によく用いられます。術中の高酸素濃度が手術部位感染の発生率を低下させる可能性を示唆するエビデンスがあります。しかしながら、酸素補給は術後の悪心・嘔吐を効果的に軽減しないようです。
外来酸素供給能力の向上に伴い、長期酸素療法(LTOT)の利用も増加しています。長期酸素療法の実施基準はすでに明確化されており、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の治療に広く用いられています。
低酸素性 COPD 患者に関する 2 つの研究が、LTOT を裏付けるデータを提供しています。最初の研究は、1980 年に実施された夜間酸素療法試験 (NOTT) で、患者は夜間 (12 時間以上) 酸素療法または持続酸素療法のいずれかに無作為に割り付けられました。12 か月および 24 か月時点で、夜間酸素療法のみを受けた患者の死亡率は高くなっています。2 番目の実験は、1981 年に実施された医学研究会議家族試験で、患者は無作為に 2 つのグループに分けられ、酸素を投与されなかったグループと 1 日あたり少なくとも 15 時間酸素を投与されたグループでした。NOTT テストと同様に、嫌気性グループの死亡率は有意に高くなりました。両試験の対象者は、最大限の治療を受け、状態が安定していて PaO2 が 55 mm Hg 未満である非喫煙患者、または PaO2 が 60 mm Hg 未満の赤血球増多症または肺性心疾患の患者でした。
これら2つの実験は、1日15時間以上酸素を補給する方が全く酸素を補給しないよりも優れており、持続酸素療法は夜間のみの治療よりも優れていることを示しています。これらの試験の包含基準は、現在の医療保険会社とATSがLTOTガイドラインを策定する際の基礎となっています。LTOTは他の低酸素性心血管疾患にも受け入れられていると推測するのは妥当ですが、現時点では関連する実験的エビデンスが不足しています。最近の多施設共同試験では、安静時の基準を満たさない、または運動のみによって引き起こされた低酸素血症を有するCOPD患者において、酸素療法が死亡率または生活の質に与える影響に差は認められませんでした。
睡眠中に血中酸素飽和度が著しく低下した患者には、医師が夜間酸素補給を処方することがあります。現在、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者におけるこのアプローチを支持する明確なエビデンスはありません。夜間の呼吸困難につながる閉塞性睡眠時無呼吸症候群または肥満性低呼吸症候群の患者の場合、酸素補給ではなく非侵襲性陽圧換気が主な治療法となります。
考慮すべきもう 1 つの問題は、飛行中に酸素補給が必要かどうかです。ほとんどの民間航空機では通常、吸入酸素分圧が約 108 mm Hg となる高度 8,000 フィートまで客室の気圧が上昇します。肺疾患のある患者の場合、吸入酸素分圧 (PiO2) の低下によって低酸素血症が起こる可能性があります。患者は旅行前に、動脈血ガス検査を含む包括的な医学的評価を受ける必要があります。地上での患者の PaO2 が 70 mm Hg 以上 (SpO2>95%) の場合、飛行中の PaO2 は 50 mm Hg を超える可能性が高く、これは一般的に最小限の身体活動に対処するのに十分であると考えられています。SpO2 または PaO2 が低い患者の場合、通常は 15% の酸素を吸入する 6 分間歩行テストまたは低酸素症シミュレーション テストを検討できます。飛行中に低酸素血症が発生した場合は、酸素摂取量を増やすために鼻カニューレから酸素を投与することができます。
酸素中毒の生化学的基礎
酸素毒性は、活性酸素種(ROS)の生成によって引き起こされます。ROSは、不対電子を持つ酸素由来のフリーラジカルで、タンパク質、脂質、核酸と反応して構造を変化させ、細胞に損傷を与えます。ミトコンドリアの正常な代謝過程においては、少量のROSがシグナル分子として生成されます。免疫細胞もROSを利用して病原体を殺傷します。ROSには、スーパーオキシド、過酸化水素(H2O2)、ヒドロキシルラジカルが含まれます。過剰なROSは、必ず細胞防御機能を超え、細胞死や細胞損傷を引き起こします。
ROS生成による損傷を抑制するため、細胞の抗酸化保護機構はフリーラジカルを中和します。スーパーオキシドディスムターゼはスーパーオキシドをH2O2に変換し、これはカタラーゼとグルタチオンペルオキシダーゼによってH2OとO2に変換されます。グルタチオンはROSによる損傷を抑制する重要な分子です。その他の抗酸化分子には、αトコフェロール(ビタミンE)、アスコルビン酸(ビタミンC)、リン脂質、システインなどがあります。ヒトの肺組織には、細胞外抗酸化物質とスーパーオキシドディスムターゼアイソザイムが高濃度に含まれているため、他の組織と比較して高濃度酸素にさらされても毒性が低くなっています。
高酸素誘発性ROS媒介性肺障害は2段階に分けられます。まず、滲出期が続きます。これは、肺胞の1型上皮細胞と内皮細胞の死滅、間質浮腫、そして滲出性好中球による肺胞への充満を特徴とします。続いて増殖期が続き、この段階では内皮細胞と2型上皮細胞が増殖し、以前は露出していた基底膜を覆います。酸素障害回復期の特徴は、線維芽細胞の増殖と間質の線維化ですが、毛細血管内皮と肺胞上皮は依然としてほぼ正常な外観を維持しています。
肺酸素毒性の臨床症状
毒性が発生する曝露レベルはまだ明らかではありません。FiO2が0.5未満の場合、臨床毒性は通常発生しません。初期のヒト研究では、ほぼ100%の酸素への曝露は、感覚異常、吐き気、気管支炎を引き起こす可能性があり、肺活量、肺拡散能、肺コンプライアンス、PaO2、pHの低下を引き起こす可能性があることが分かっています。酸素毒性に関連するその他の問題としては、吸収性無気肺、酸素誘発性高炭酸ガス血症、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)、新生児気管支肺異形成症(BPD)などがあります。
吸収性無気肺。窒素は酸素に比べて血流への拡散が非常に遅い不活性ガスであり、肺胞の拡張を維持する役割を果たします。100%酸素を使用する場合、酸素吸収速度が新鮮ガスの供給速度を上回るため、肺胞換気灌流比(V/Q)が低い部位では窒素欠乏により肺胞虚脱が生じる可能性があります。特に手術中は、麻酔や麻痺によって残存肺機能が低下し、小気道や肺胞の虚脱が促進され、無気肺が急速に発症する可能性があります。
酸素誘発性高炭酸ガス血症。重症COPD患者は、病状の悪化に伴い高濃度酸素に曝露されると、重度の高炭酸ガス血症を発症しやすい。この高炭酸ガス血症のメカニズムは、低酸素血症による呼吸促進能力の阻害である。しかし、どの患者においても、程度の差はあれ、他に2つのメカニズムが関与している。
COPD患者の低酸素血症は、低V/Q領域における肺胞酸素分圧(PAO2)の低下が原因です。この低V/Q領域による低酸素血症への影響を最小限に抑えるため、肺循環の2つの反応、すなわち低酸素性肺血管収縮(HPV)と高炭酸ガス性肺血管収縮により、換気の良い領域に血流が移行します。酸素補給によりPAO2が上昇すると、HPVは大幅に低下し、これらの領域への灌流が増加し、結果としてV/Q比の低い領域が生じます。これらの肺組織は酸素が豊富です。しかし、CO2を排出する能力は低下します。これらの肺組織への灌流増加は、換気の良い領域を犠牲にすることを代償とし、以前のように大量のCO2を排出できなくなり、高炭酸ガス血症につながります。
もう一つの理由は、ハルデン効果の弱化です。これは、酸素化された血液と比較して、脱酸素化された血液はより多くの二酸化炭素を運搬できることを意味します。ヘモグロビンが脱酸素化されると、アミノエステルの形でより多くのプロトン(H+)と二酸化炭素と結合します。酸素療法中に脱酸素化ヘモグロビン濃度が低下すると、二酸化炭素とH+の緩衝能も低下し、静脈血の二酸化炭素運搬能力が低下し、PaCO2の上昇につながります。
慢性CO2貯留患者やハイリスク患者、特に極度の低酸素血症患者に酸素を供給する場合、FIO2を微調整してSpO2を88%~90%の範囲に維持することが極めて重要です。酸素濃度の調整が不十分だと悪影響が出る可能性があることは、複数の症例報告で示されています。CODPの急性増悪で入院中の患者を対象としたランダム化試験は、このことを紛れもなく証明しています。酸素制限のない患者と比較して、SpO2を88%~92%の範囲に維持するために酸素を補充するようにランダムに割り当てられた患者の死亡率は、有意に低かった(7%対2%)。
ARDSとBPD。酸素毒性がARDSの病態生理と関連していることは、古くから知られていました。ヒト以外の哺乳類では、100%酸素への曝露はびまん性肺胞損傷を引き起こし、最終的には死に至る可能性があります。しかし、重症肺疾患患者における酸素毒性の正確な証拠は、基礎疾患による損傷と区別することが困難です。さらに、多くの炎症性疾患は抗酸化防御機能の亢進を引き起こす可能性があります。そのため、ほとんどの研究では、過剰な酸素曝露と急性肺損傷(ARDS)との相関関係を示すことができていません。
肺硝子膜疾患は、表面活性物質の欠乏によって引き起こされる疾患で、肺胞の虚脱と炎症を特徴とします。硝子膜疾患を患う未熟児は、通常、高濃度酸素の吸入を必要とします。酸素毒性はBPDの発症における主要な要因と考えられており、人工呼吸器を必要としない新生児にも発症することがあります。新生児は細胞の抗酸化防御機能がまだ十分に発達・成熟していないため、高酸素障害に特にかかりやすいです。未熟児網膜症は、低酸素/高酸素ストレスの反復に関連する疾患であり、この影響は未熟児網膜症においても確認されています。
肺酸素毒性の相乗効果
酸素毒性を増強する薬剤がいくつかあります。酸素はブレオマイシンによって産生される活性酸素種(ROS)を増加させ、ブレオマイシン加水分解酵素を不活性化します。ハムスターでは、高酸素分圧がブレオマイシン誘発性肺障害を悪化させる可能性があり、症例報告では、ブレオマイシン治療を受け、周術期に高濃度の酸素分圧(FIO2)に曝露された患者にARDSが発生したことも報告されています。しかし、前向き試験では、高濃度酸素曝露、過去のブレオマイシン曝露、および重度の術後肺機能障害との関連性は示されませんでした。パラコートは市販の除草剤であり、酸素毒性を増強する別の因子です。したがって、パラコート中毒でブレオマイシンに曝露された患者を扱う際には、FIO2を可能な限り最小限に抑える必要があります。酸素毒性を悪化させる可能性のある他の薬剤には、ジスルフィラムやニトロフラントインなどがあります。タンパク質と栄養素の欠乏は、グルタチオンの合成に不可欠なチオール含有アミノ酸の不足、および抗酸化ビタミン A と E の不足により、酸素による大きなダメージにつながる可能性があります。
他の臓器系における酸素毒性
高酸素症は肺以外の臓器に毒性反応を引き起こす可能性があります。大規模な多施設共同後ろ向きコホート研究では、心肺蘇生(CPR)成功後の高酸素レベルと死亡率の上昇との関連が示されました。この研究では、CPR後にPaO2が300mmHgを超えた患者は、血中酸素濃度が正常または低酸素血症の患者と比較して、院内死亡リスク比が1.8(95% CI、1.8~2.2)であることが分かりました。死亡率上昇の原因は、ROS媒介性高酸素再灌流障害によって引き起こされる心停止後の中枢神経系機能の低下です。最近の研究では、救急外来での挿管後に低酸素血症を呈した患者の死亡率上昇も報告されており、これはPaO2上昇の程度と密接に関連しています。
脳損傷および脳卒中の患者において、低酸素血症のない患者への酸素投与は有益ではないようです。ある外傷センターで実施された研究では、血中酸素濃度が正常な患者と比較して、高酸素療法(PaO2>200mmHg)を受けた外傷性脳損傷患者は、退院時の死亡率が高く、グラスゴー・コーマ・スコアが低いことが示されました。高圧酸素療法を受けた患者を対象とした別の研究では、神経学的予後が不良であることが示されました。大規模な多施設共同試験では、低酸素血症(酸素飽和度>96%)のない急性脳卒中患者への酸素補給は、死亡率および機能的予後に有益性を示しませんでした。
急性心筋梗塞(AMI)では、酸素補給は一般的な治療法ですが、そのような患者に対する酸素療法の有効性については依然として議論が続いています。酸素は、低酸素血症を併発する急性心筋梗塞患者の治療に不可欠であり、命を救う可能性があります。しかし、低酸素血症がない場合の従来の酸素補給のメリットはまだ明らかになっていません。1970年代後半、合併症のない急性心筋梗塞患者157名を対象に、二重盲検ランダム化試験が実施され、酸素療法(6 L/分)を受けた患者と酸素療法を受けなかった患者が比較されました。酸素療法を受けた患者では、洞性頻脈の発症率が高く、心筋酵素の上昇も大きかったものの、死亡率には差がなかったことが判明しました。
低酸素血症のないST上昇型急性心筋梗塞患者において、8L/分の経鼻カニューレ酸素療法は、大気吸入と比較して有益性が低い。6L/分の酸素吸入と大気吸入を比較した別の研究では、急性心筋梗塞患者の1年死亡率および再入院率に差は認められなかった。院外心停止患者において、血中酸素飽和度を98~100%および90~94%にコントロールしても、有益性は認められない。高酸素投与が急性心筋梗塞に及ぼす潜在的な有害作用としては、冠動脈収縮、微小循環血流分布の乱れ、機能的酸素シャントの増加、酸素消費量の減少、再灌流が成功した領域における活性酸素(ROS)障害の増加などがあげられる。
最後に、臨床試験とメタアナリシスにより、重症入院患者の適切な SpO2 目標値が調査されました。集中治療室の患者 434 名を対象に、保守的酸素療法 (SpO2 目標 94%~98%) と従来療法 (SpO2 値 97%~100%) を比較する単施設オープンラベル無作為化試験が実施されました。保守的酸素療法を受けるように無作為に割り当てられた患者の集中治療室での死亡率は改善し、ショック、肝不全、菌血症の発生率が低下しました。その後のメタアナリシスには、脳卒中、外傷、敗血症、心筋梗塞、緊急手術など、さまざまな診断を受けた 16,000 名を超える入院患者を対象とした 25 件の臨床試験が含まれていました。このメタアナリシスの結果、保守的酸素療法戦略を受けた患者の院内死亡率が上昇することが示されました (相対リスク 1.21、95% CI 1.03-1.43)。
しかし、その後行われた2つの大規模試験では、肺疾患患者の人工呼吸器非装着日数やARDS患者の28日生存率に対する保守的な酸素療法戦略の影響は示されませんでした。最近、人工呼吸器を装着している2,541人の患者を対象とした研究では、3つの異なるSpO2範囲(88%~92%、92%~96%、96%~100%)内での目標酸素補給は、28日以内に人工呼吸器を装着していない患者の生存日数、死亡率、心停止、不整脈、心筋梗塞、脳卒中、気胸などの転帰に影響を与えないことが明らかになりました。これらのデータに基づき、英国胸部学会のガイドラインでは、ほとんどの成人入院患者に対して94%~98%の目標SpO2範囲を推奨しています。これは妥当な値です。なぜなら、この範囲内のSpO2(パルスオキシメーターの誤差±2%~3%を考慮)は、PaO2で65~100mmHgの範囲に相当し、血中酸素濃度として安全かつ十分な値だからです。高炭酸ガス血症性呼吸不全のリスクがある患者の場合、酸素による高炭酸ガス血症を回避するために、88%~92%がより安全な目標値となります。
投稿日時: 2024年7月13日